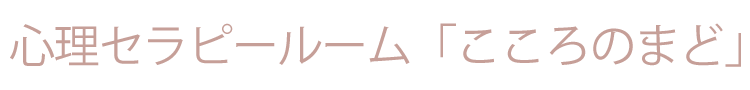「ベッドに入っても、頭の中がグルグル…」
「休みの日なのに、気持ちが休まらない」
「ぼーっとしたいのに、ついあれこれ考えてしまう」
こんな経験はありませんか?
実はこれは、次のような心と体の癖がある人にとって、珍しいことではなく、とても自然な心と体の反応なんです。
でも、ずっと思考が休めないのは、落ち着くこと、リラックスすることができず
体も休めず、段々と疲れが蓄積してしまいます。

理由を知ると、解決してゆっくりと心と体が休められるようになりますので、安心してくださいね。
なぜ思考が休まらないのか?
脳の危険探知機能が働いている
私たちは、危険を回避するために未来を予測する機能があります。
「大丈夫かな?」「忘れてないかな?」と考えてしまうのは、身を守ろうとする本能的な働きなのです。
また、過去の失敗を繰り返すことを恐れて、
「失敗しないように」「ちゃんとするためには…」と考えることもあります。
完璧主義な人は、このパターンにはまりやすいですね。
トラウマや、嫌な感情・感覚を感じないようにするための防衛反応
過去にトラウマや、不安や悲しみなど嫌な感情・感覚を感じた経験がある人は
それに触れることを無意識に「これ以上傷つきたくない」
「嫌な感情を感じたくない」と避けようとして
体を緊張させたり、思考を忙しく働かせ続けることがよくあります。
だから、「ゆったりと休みたい」と思っても
緩むと不安や恐怖が押し寄せてしまうような感覚を覚えるので
思考している方がマシ、ということになってしまいます。
また、このような人は、自分の気持ちには鈍感で
かつ、不安やストレスに過敏で囚われやすい傾向もあるために
思考することで安心しようとして
「あの人に嫌われたかも」
「どうしてあんなこと言ったんだろう」
「あの時言われたことに腹が立つ」
「どうしたらいいんだろう」など
過去のことも、未来のことも、アレコレと考えてしまうのです。
いずれにしても、考えすぎることは、疲れる、休めない、眠れないなどにつながってしまいます。
そして、次のような理由で
「こんなに考えるのに、考えがまとまったり、問題解決に至らない」ということも多いのです。
行動が伴わないこともある
「思考が強い人=よく考える人」は、
一見しっかりしていて行動力もありそうですが
実際には行動が伴わないことが多いという傾向があります。
●考えすぎてエネルギーを消耗する
●完璧を求めすぎる
●失敗を恐れすぎる
●考えていることで安心する
シミュレーションや、リスクを考えすぎて疲れたり
失敗やリスクばかり考えてしまって行動に移せなくなったり
「まだどうしたらいいかわからないから」と言い訳したりするので
「実際の行動が伴わない」=悩みが解決しない、物事が前進しない、ということが起こります。
すると、また「考えてしまう、、、」という悪循環に陥ります。

解決のために
考えすぎることは、あなたの「性格」や、「ダメなこと」ではありません。
でも、考えすぎをやめて、心と体を休められるようになるためには
まず、心理的なケアとしては
過去のトラウマを癒やし、自分の感情や感覚を安心して感じられるようになることが大切です。
それから、実際の行動として
・思考を書き出してみる
・深呼吸やストレッチ、散歩をするなど、体を緩める習慣を
・自分の五感(視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚)を使うことを意識してみる
・小さなことからでいいので、考えたことを行動に移す など
少しずつやってみてくださいね。

私たちには、しっかりと考えることが必要なこともとても多いです。
思考することが悪いのではありません。
でも、不要な思考癖は手放して
オンとオフ(心も体もリラックスできる時間)の切り替えをして健康的でいたいですね。
では、また。